
長時間労働の原因と、効果的な削減方法とは
2019年4月に「働き方改革」が施工され、長時間労働に対する取り締まりがより厳しくなりましたが、実際はまだまだ残業が減らず、遅くまで仕事をしている人は少なくないでしょう。 長時間労働を減らしたいと思っているにもかかわらず、なぜスムーズに残業時間を削減する事ができないのでしょうか。 今回は「長時間労働が減らない原因」「長時間労働によるデメリット」「長時間労働の削減方法」をご紹介していきます。

2019年4月に「働き方改革」が施工され、長時間労働に対する取り締まりがより厳しくなりましたが、実際はまだまだ残業が減らず、遅くまで仕事をしている人は少なくないでしょう。 長時間労働を減らしたいと思っているにもかかわらず、なぜスムーズに残業時間を削減する事ができないのでしょうか。 今回は「長時間労働が減らない原因」「長時間労働によるデメリット」「長時間労働の削減方法」をご紹介していきます。

この数年、コロナウイルスの予防や働き方改革の一環として、出退勤時間の取り決めを独自に工夫する企業が多くなりました。そうした取り組みの一つとして「時差出勤」を導入した企業は多いのではないでしょうか。 通勤ラッシュの時間を避け、ストレス緩和に繋がるとして期待されている時差出勤ですが、効果的に取り入れないと、かえって従業員の負担となってしまう可能性があります。

世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大したことにより、働き方が大きく変化し、日本でもテレワークの導入が急激に浸透しました。移動時間から解放され、ワークライフバランスを充実させる事が出来るテレワークですが、その反面、退勤後の隠れ残業やメリハリのつけられない長時間労働がまん延しているのも現実です。

新型コロナウイルスの感染拡大により「働き方の多様化」が進み、テレワークの一環である「在宅勤務」を導入する企業が増えてきました。そして感染の収束が予見できない中、長期的に在宅勤務の継続を行う事を決定した企業も多いのではないでしょうか。

2019年の働き方改革法案にて、長時間労働の是正や有給取得率促進のため様々な規制が設けられましたが、そのなかでも努力義務とされている「勤務間インターバル制度」についてご存知でしょうか。

日本では昔から、他国と比べて長時間労働を行う事が美徳とされてきました。日本人特有のコツコツと真面目に働く性格から生まれた社会文化だと思われますが、近年では長時間労働による過労死や、残業時間としてカウントされないサービス残業等の多くの問題がニュースでも取り上げられるようになりました。

企業が遂行しなければならない健康管理の項目にはどのようなものがあるのでしょうか。

「勤務間インターバル」という言葉を聞いたことはございますでしょうか。 「勤務間インターバル」とは実質的な労働時間を短くするといった制度のことを言います。

深夜まで続く残業や過度な休日労働は、働く人々の心身に大きな健康被害をもたらすリスクを伴っています。また労働力人口が減少する中、女性や高齢者、障がい者、外国人など、より多様な層の人材に目を向けてそれぞれの能力に合った多様な働き方を実現がすることが求められています。
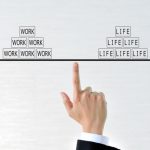
昨今の日本では、労働人口の減少による人材不足が深刻と言われています。一人でも多くの労働者が快適に業務を遂行できるよう、ワークライフバランスに合わせた働き方が推奨されていますが、なかでも「短時間勤務制度(以下:時短勤務)」という働き方を耳にする事は多いのではないでしょうか。